このページでは、
理科のスケッチの仕方とルール、ルーペの使い方
を解説します。
「理科のスケッチ」は絵が上手なことより、
ルールを守って書くことが大切です。
・
・
1.スケッチの仕方(中学理科)
では、理科でのスケッチの仕方をまとめます!
1.よく削った細い鉛筆を使い、細い線で書く
2.線を重ね書きしたり、影をつけたりしない
3.背景(観察する物以外)は書かない
4.色はつけない
5.言葉を書いてもよい
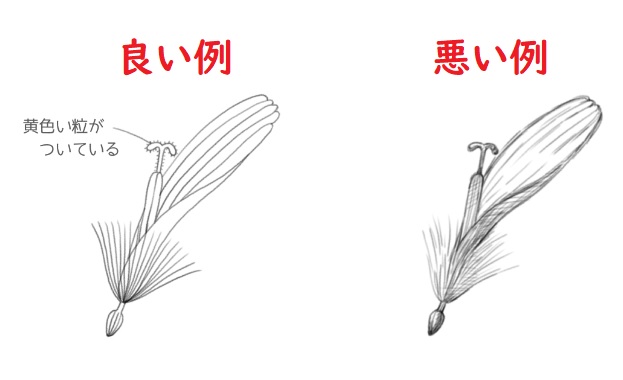
スケッチの仕方について詳しく説明
1.よく削った細い鉛筆を使い、細い線で書く
理科のスケッチは、細い鉛筆で細い線を、はっきりと見やすく書くことが大切です。
1本1本の線をていねいに書きましょう。
2.線を重ね書きしたり、影をつけたりしない
理科のスケッチは、影を付けないことが特徴です。
「実際に存在しない線は書かない」が大切です。
黒く見えてもぬりつぶす必要はありません。
3.背景(観察する物以外)は書かない
「花を書こう」と決めたら花だけを書けばOKです。
後ろに背景が見えても、書かなくて大丈夫です。
4.色はつけない
色はつけずに鉛筆のみで白黒で書けばOKです。
モノクロで表現をします。
5.言葉を書いてもよい
スケッチで書き表せない所は、言葉で表現しても大丈夫です。
見た人が良くわかるように、説明を加えましょう。
あまりにも言葉が多くなる場合は、別の紙にメモを取りましょう。
スケッチの仕方まとめ
1.よく削った細い鉛筆を使い、細い線で書く
2.線を重ね書きしたり、影をつけたりしない
3.背景(観察する物以外)は書かない
4.色はつけない
5.言葉を書いてもよい
・
・
2.ルーペの使い方(中学理科)
ルーペは「拡大鏡(かくだいきょう)」とも言い、わかりやすく言うと虫眼鏡です。
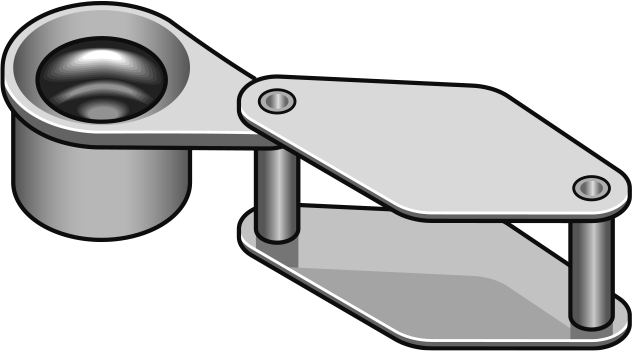
中学理科で使うルーペは、「凸レンズ(とつレンズ)」といって、中央がふくらんだレンズを使っています。
ルーペの使い方
ルーペには正しい使い方(動かし方)があります。
1.観察するものが動かせるとき
観察するものが動かせるときのルーペの使い方は
1.ルーペを目に近づけて持つ
2.観察するものを動かす
という手順で、よく見える位置を探します。

2.観察するものが動かせないとき
観察するものが動かせないときのルーペの使い方は、
1.ルーペを目に近づけて持つ
2.顔(頭)を動かす
という手順で、よく見える位置を探します。

ルーペの使い方のまとめ
ルーペは必ず「目に近づけてもつ」
物体が動かせるなら動かし、
物体が動かせないなら顔を動かしましょう。


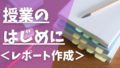

コメント